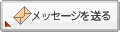2016年03月28日
徒然に
久々にB-fight
通常ゲームばかりだったので
午前は雨でしたので 午後から少しだけですけど
今回の反省
1VS1でしたので ほんとに久々かも
思ったよりも 調子もよかったかと・・・・
当方はいつも相手の位置と視界を意識します
意識した上で 相手射線を狭めて 当方の射線を一つに絞る感じです
ある意味ではごく短時間な「待ち」の状況を作る感じですが
そのためには 相手の情報と リスクを管理する必要があります
このブログでも何度も書いてますが
相手をびっくりさせる という状況を作りたいわけです
これは書き方を変えると 相手より早い段階で 射撃姿勢を作っているという
先読みのような状況と
逆に相手に読まれないように位置を変えるという
リスク管理の両方です
カン といえばカンなのですが
バリケードに入った相手の出てくる方向は 単純に右か左です
相手が右利きであれば 当方から見て左から出てくることが確率として高いとすれば
左から出てきた場合の相手射線をバリでふさいで
右から出てきたところで撃てる状況を作る意識です
その時々で狙いを変えることで
相手に読まれないようにしつつ
相手の動きを読んでいくイメージです
通常のゲームでは もっと単純に目線や銃口で相手の意識の方向が見えますが
B-fight特に 1VS1の場合 個人で陽動をかける必要があります
実際には 相手により状況はめまぐるしく変わるわけで
その時々で イニシアチブは交互に動くわけですから
ゲームの流れを読みつつ 先を読み 思い通りの状況に近づけていかないと
勝てないわけです
まぁそうはいっても 当方もできない場面もありますので
精進が必要ということです
通常ゲームばかりだったので
午前は雨でしたので 午後から少しだけですけど
今回の反省
1VS1でしたので ほんとに久々かも
思ったよりも 調子もよかったかと・・・・
当方はいつも相手の位置と視界を意識します
意識した上で 相手射線を狭めて 当方の射線を一つに絞る感じです
ある意味ではごく短時間な「待ち」の状況を作る感じですが
そのためには 相手の情報と リスクを管理する必要があります
このブログでも何度も書いてますが
相手をびっくりさせる という状況を作りたいわけです
これは書き方を変えると 相手より早い段階で 射撃姿勢を作っているという
先読みのような状況と
逆に相手に読まれないように位置を変えるという
リスク管理の両方です
カン といえばカンなのですが
バリケードに入った相手の出てくる方向は 単純に右か左です
相手が右利きであれば 当方から見て左から出てくることが確率として高いとすれば
左から出てきた場合の相手射線をバリでふさいで
右から出てきたところで撃てる状況を作る意識です
その時々で狙いを変えることで
相手に読まれないようにしつつ
相手の動きを読んでいくイメージです
通常のゲームでは もっと単純に目線や銃口で相手の意識の方向が見えますが
B-fight特に 1VS1の場合 個人で陽動をかける必要があります
実際には 相手により状況はめまぐるしく変わるわけで
その時々で イニシアチブは交互に動くわけですから
ゲームの流れを読みつつ 先を読み 思い通りの状況に近づけていかないと
勝てないわけです
まぁそうはいっても 当方もできない場面もありますので
精進が必要ということです
2016年03月17日
徒然に
先日のゲームで当方なら と思うこと
ただの妄想ですけど・・・・
まず5VS3という戦力比を考えると
1VS1を三つ作っても2余る
そうすると ランチェスターの定理 を引用して
1VS3 1VS1 1VS1 という状況を作れれば
1VS3での勝利は3側となる
3が無傷であれば
4VS1 1VS1 あるいは 3VS1 2VS1 となり
有利に進める
3が目減りしても 1が3を全滅させることがなければ
数的優位は常に維持できる
こう考えると 1VS3での勝敗が チームの勝敗に影響を与え続ける
1VS3で勝つには
多方向からの射撃 あるいは相手の動きを止めて近づく等の 戦術が必要になる
この場合1VS1で相対している味方は 相手が動かないまたは手が出せないように
する必要があり勝敗よりは現状維持と 倒されないことが重要となるので無理はしない
また 1VS3はできるだけ時間をかけないで勝つ必要がある
これは理想論
当方ならば 1VS1 1VS1 1VS1 であまりの2が流動的に
各ペアに一時的に2VS1 あるいは3VS1と乱入することで
数的優位を作り 相手の邪魔な目標となるようにする
相手のミスを誘いつつ まず一人倒すことが前提となる
また戦況が有利に動いた場合は 高所にコントロールを置いて
相手の情報を常に把握する
あるいは距離をとり 情報の共有化を図り 全体としての行動を決める
もちろん個々の動きは制御できない場面があるので
フォローを中心として
移動範囲を広く取り
味方の位置情報を常に把握するようにする
型を知らない場合は できるだけ タイミングを声に出す
倒すことより フラッグアタックの回数を増やすように味方が倒されないことを重視する
また相手の出鼻をくじいて 混乱させることもある
初めに描いたポジションは 上手くいく場合もあるが 基本的に失敗すると考えておく
その場合の立て直し方 として 常に味方との情報だけは密に連絡を取る
もし数的優位が崩れそうな場合には 早い段階で 「待ち」の準備をする
早ければ早いほど 相手に情報が伝わらず 時間を稼ぎやすい
逆に優勢に転じた時に遅れないように フィールドの距離感を常に意識する
とは思うものの そんなにうまくいかないですけどね
ただの妄想ですけど・・・・
まず5VS3という戦力比を考えると
1VS1を三つ作っても2余る
そうすると ランチェスターの定理 を引用して
1VS3 1VS1 1VS1 という状況を作れれば
1VS3での勝利は3側となる
3が無傷であれば
4VS1 1VS1 あるいは 3VS1 2VS1 となり
有利に進める
3が目減りしても 1が3を全滅させることがなければ
数的優位は常に維持できる
こう考えると 1VS3での勝敗が チームの勝敗に影響を与え続ける
1VS3で勝つには
多方向からの射撃 あるいは相手の動きを止めて近づく等の 戦術が必要になる
この場合1VS1で相対している味方は 相手が動かないまたは手が出せないように
する必要があり勝敗よりは現状維持と 倒されないことが重要となるので無理はしない
また 1VS3はできるだけ時間をかけないで勝つ必要がある
これは理想論
当方ならば 1VS1 1VS1 1VS1 であまりの2が流動的に
各ペアに一時的に2VS1 あるいは3VS1と乱入することで
数的優位を作り 相手の邪魔な目標となるようにする
相手のミスを誘いつつ まず一人倒すことが前提となる
また戦況が有利に動いた場合は 高所にコントロールを置いて
相手の情報を常に把握する
あるいは距離をとり 情報の共有化を図り 全体としての行動を決める
もちろん個々の動きは制御できない場面があるので
フォローを中心として
移動範囲を広く取り
味方の位置情報を常に把握するようにする
型を知らない場合は できるだけ タイミングを声に出す
倒すことより フラッグアタックの回数を増やすように味方が倒されないことを重視する
また相手の出鼻をくじいて 混乱させることもある
初めに描いたポジションは 上手くいく場合もあるが 基本的に失敗すると考えておく
その場合の立て直し方 として 常に味方との情報だけは密に連絡を取る
もし数的優位が崩れそうな場合には 早い段階で 「待ち」の準備をする
早ければ早いほど 相手に情報が伝わらず 時間を稼ぎやすい
逆に優勢に転じた時に遅れないように フィールドの距離感を常に意識する
とは思うものの そんなにうまくいかないですけどね
2016年03月16日
徒然に
いきなり寒い・・・
今回の反省
久々にチームの人数が集まりTTFへ
作為的に 若者VS中高年?となりました
当方は中高年側 当たり前ですが
勝敗は別として
基礎の戦術を共通認識している味方同士だと
情報のやり取りがスムーズです
久々に前だけ見るゲームをしました
ゲーム中の戦況は随時変わります
それでも戦況の認識がチームで共通であれば
声をかける必要もなく
次の行動を行えるわけです
もちろん年月はかかりますが
ある意味での完成系だと思います
今回はブランクも含めて
時間のかかる部分もありましたけど
逆にブランクがあってもできるのは
それはそれで凄いことかと・・・
声で確認していることは
エリアの相手数位ですが
そこにある情報量はもっと多いわけです
一人一人が味方に合わせてすべきことを考え行動するゲームは面白いし充実感があります
ただ基本的に当方が猪突猛進型で合わせてもらうことが多いので
当方自身も合わせられるように精進しないとまずいです
今回の反省
久々にチームの人数が集まりTTFへ
作為的に 若者VS中高年?となりました
当方は中高年側 当たり前ですが
勝敗は別として
基礎の戦術を共通認識している味方同士だと
情報のやり取りがスムーズです
久々に前だけ見るゲームをしました
ゲーム中の戦況は随時変わります
それでも戦況の認識がチームで共通であれば
声をかける必要もなく
次の行動を行えるわけです
もちろん年月はかかりますが
ある意味での完成系だと思います
今回はブランクも含めて
時間のかかる部分もありましたけど
逆にブランクがあってもできるのは
それはそれで凄いことかと・・・
声で確認していることは
エリアの相手数位ですが
そこにある情報量はもっと多いわけです
一人一人が味方に合わせてすべきことを考え行動するゲームは面白いし充実感があります
ただ基本的に当方が猪突猛進型で合わせてもらうことが多いので
当方自身も合わせられるように精進しないとまずいです
2016年03月16日
徒然に
前回の続き・・・・
見せる場面と見せない場面ですが
根本には戦術的な理由があると思うわけです
これがすべてではないですが
たとえば スタート時に相手に姿を見せることで
注目させ先行する味方を援護すること
この場合相手との距離が遠いことが多いことから
姿を見せる量(時間?)を大きくすることができるわけです
逆に先行する場合はこのタイミングを有効に利用することで
相手に位置情報を与えないことを念頭に置いて
姿を見せずに距離を縮めるわけです
いわゆる陽動戦術なわけですが
特に人数が少ないゲームでは 相手の目 銃口をいかにコントロールして
距離を縮めるかがポイントとなるわけです
また
フラッグアタックの場面で相手の位置がわからない場合
積極的に姿を見せて
相手に撃たれることで ある意味では無理やり
情報を得る方法もあるわけです
全てはチームとしての練度といいますか
ある程度の基本となる戦術基礎が
共通認識していることが必要ですが
最小限のリスクで最大限の効果を得ることが重要だと思うわけです
サバイバルゲームはチームで勝敗を競うことが主な目的だとすれば
チームという単位でのレベルを上げるのは
必要不可欠です
もちろん勝敗だけではありませんが
そこを無視してしまうと
ゲームという大前提がなくなる気がします
個人のレベルアップだけでチームが勝てるほどあまくは無いですし
たかが知れてます
個人的な印象ですが
素晴らしく的当てが上手い(素早く正確に当てる)人が一人いるチームより
チーム全体で意思のある行動を取るチームの方がチームの勝率は良いと感じます
味方の状況で自分の行動を合わせる
これをみんなができる人が上手いと感じるわけです
見せる場面と見せない場面ですが
根本には戦術的な理由があると思うわけです
これがすべてではないですが
たとえば スタート時に相手に姿を見せることで
注目させ先行する味方を援護すること
この場合相手との距離が遠いことが多いことから
姿を見せる量(時間?)を大きくすることができるわけです
逆に先行する場合はこのタイミングを有効に利用することで
相手に位置情報を与えないことを念頭に置いて
姿を見せずに距離を縮めるわけです
いわゆる陽動戦術なわけですが
特に人数が少ないゲームでは 相手の目 銃口をいかにコントロールして
距離を縮めるかがポイントとなるわけです
また
フラッグアタックの場面で相手の位置がわからない場合
積極的に姿を見せて
相手に撃たれることで ある意味では無理やり
情報を得る方法もあるわけです
全てはチームとしての練度といいますか
ある程度の基本となる戦術基礎が
共通認識していることが必要ですが
最小限のリスクで最大限の効果を得ることが重要だと思うわけです
サバイバルゲームはチームで勝敗を競うことが主な目的だとすれば
チームという単位でのレベルを上げるのは
必要不可欠です
もちろん勝敗だけではありませんが
そこを無視してしまうと
ゲームという大前提がなくなる気がします
個人のレベルアップだけでチームが勝てるほどあまくは無いですし
たかが知れてます
個人的な印象ですが
素晴らしく的当てが上手い(素早く正確に当てる)人が一人いるチームより
チーム全体で意思のある行動を取るチームの方がチームの勝率は良いと感じます
味方の状況で自分の行動を合わせる
これをみんなができる人が上手いと感じるわけです
2016年03月07日
徒然に
若いっていいな・・・・・
今回の反省
TTFで通常ゲームしてきました
色々ありますが
若いっていいなぁと・・・・
反省としては
まだ少し判断の遅い部分もあったかなと
まぁリハビリです (言い訳です)
ちょっと気になったことを
当方の主観で・・・・
見せる場面と見せない場面があると思うわけです
チームとして勝つことを目的にする以上
リスクを負うべき場面はあります
姿を見せるべき時と 見せない時 この二つに
共通するのは味方への情報共有であるわけで
この切り替えは重要な部分でもあるわけです
今後少し書くかもしれませんが
今日は眠いのでここまで
今回の反省
TTFで通常ゲームしてきました
色々ありますが
若いっていいなぁと・・・・
反省としては
まだ少し判断の遅い部分もあったかなと
まぁリハビリです (言い訳です)
ちょっと気になったことを
当方の主観で・・・・
見せる場面と見せない場面があると思うわけです
チームとして勝つことを目的にする以上
リスクを負うべき場面はあります
姿を見せるべき時と 見せない時 この二つに
共通するのは味方への情報共有であるわけで
この切り替えは重要な部分でもあるわけです
今後少し書くかもしれませんが
今日は眠いのでここまで