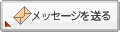2012年03月23日
徒然に
春も近いっていうのに
寒くて凹みます
今回は少しですがブラインドと連携について考察したい感じです
いつも書いていますが戯言ですので
ご容赦願います
前々回のブログで「ブラインド」なんてしたり顔で書いていますが
基本的には当方が勝手に言っているだけですので
サバイバルゲーム業界全般で使える用語ではありませんのであしからず
情報戦であると仮定している以上
その情報は位置情報であると書きました
情報を得るやり方は過去にも書きましたので
詳しい説明は避けますが
羅列すると
・視覚
・聴覚
ではないでしょうか
細かくすればもっと細分化しますが
細かいと分類しきれませんので
長所と短所についても過去に書いていますので割愛
ポイントとして相手の隠れているバリケードは
相手が当たらないようにするためだけなのか?ということです
「何言ってんだ」って感じですが
バリケードに隠れるというのはもちろん相手からの射撃に対して
当たらないようにするためです
当然ですね
しかしですね
ある一定の距離であれば
実は自分を相手から隠してくれるブラインドになるということです
この感覚は文章にしても伝わらないと思うのですが
意識するとわかるかもしれません
例えばですが
バリケードに相手がいます
自分も相手バリケードから5mのバリケードにいます
相手がバリの左から銃を出してこちらを撃ってきましたので
バリにへばりつき相手の射撃が止むのを待ちます
相手の射撃が止みました
相手の情報を得るためにバリから様子を伺います
相手がいることは確実ですが
相手はバリから顔を出してません
こんな状態があったとします
前提条件としてこの二人以外は周りに人がいないため連携もできませんし
相手の援護も無いとします
この時に相手が隠れているバリケードは
自分にとって相手の目隠しになるということです
先に挙げた情報の取得方法の「視覚」が相手は使えません
この瞬間に移動(有利なポジションに)できないかということです
もちろん例に関して言えば1:1の状況ですので
ゲームで使える状況としては少ないかもしれませんが
フィールドにあるバリや構造物を使い視覚の分断が出来るエリアを認識し味方との連携が
確立すれば実際にはよくある状況なのかもしれません
先ほど書いた例のような状態で
どのように行動するかを考えてみてください
よくありがちなのは相手が顔を出した瞬間狙えるように
自分がバリから狙って待つという戦法ではないでしょうか
もちろん間違っていませんし
うまくイニシアチブがとれているわけで
当方も良くやります
しかし
時間制限のあるゲームということを加味すると
相手が出てくるまで待つというのは
相手側にイニシアチブを取られている可能性もあるわけです
特にゲーム後半であれば逆転を狙うより時間切れを狙う戦術に切り替えてくるでしょう
時間切れであれば勝敗はないわけで引き分けです
そういう意味では相手の戦法にハマっていると言えます
ここで言いたいのは
相手にイニシアチブを取られずに
言い方としてどうかとは思いますが効率的に進行する前提として考えれば
相手の出方を待つには時間がかかりすぎかもしれません
もちろん毎回うまくいくとは限りませんが
膠着というゲームはなくなると思うわけです
前にも書きましたが
この遊びに関しては時間が経てば人数が減ります
人数が減ることでこのような状態も生まれるやすくなるわけです
そして情報の取得が大事だとも書きました
逆を言えばいかに自分の情報を隠すかでもあります
特に「視覚」は情報取得の大きなウエイトを占めていると思っています
だからこそバリにへばりつけばその方向に対して
情報の取得が困難になると考えればいいわけです
これは相手も一緒ですし自分にもあてはまることになるので
どちらがうまく使えるか(イニシアチブが取れるか)ということにつながってくるわけです
ブラインドには色々な方法があると思います
・ある程度の距離があるバリケードや構造物を使う方法
・相手の隠れているバリケードや構造物を使う方法
・フィールドの高低差や死角を使う方法
とりあえず三つ書き出しましたがどれも自分との距離が一定あいていることが重要です
実は自分がバリケードにへばりつく(書き方がいいかわかりませんが)場合には
自分にとっての利がない場合が多い気がします(経験上ですが)
もちろん前提としてバリケードは弾除けです
しかしそれだけでないことが重要だと思うわけです
例えば
相手への射撃牽制をしている間は
相手はバリケードにへばりつきます
その場合相手の視覚情報は0に近くなるわけです
逆にそのような「心理情報」をこちらが取得すれば
有利な位置へ動くことも可能になります
ゲームが情報戦である以上相手に動く瞬間を見られないことは
大きなアドバンテージになると思うわけです
さてここまでブラインドについて書きましたが
これを踏まえたうえで連携を考察する場合どうなるでしょうか?
「連携」と聞くと何を連想しますか
SWATのようなクリアリングでしょうか
当方の経験上では相手を倒すための騙し合いの手段と考えています
サッカーでフォアードがキーパーからゴールを奪うのに壁パスとかスルーしたり
後方からマークしてない人間がゴール前に入ってくる動きを見たことありませんか
サバイバルゲームの連携もあれに近いのではないかと考えています
どういうことかというと
ある意味で陽動ということです
サッカーにしてもボールを持っている人間に注意が行くわけです
そしてゴールを決めるときには
ボールを持っていない人間の動き「オフ ザ ボール」の動きが左右するなんて
解説で聞きますが
ゲームも同じことが言えるのではないでしょうか
鉄砲を撃っている人間はやはり注目を浴びます
なぜなら情報戦と踏まえて
聴覚情報を発信し続けているわけです
しかも実体験上みんなが撃っているときは体のどこかが保護されていないと知っているわけです
そうすると自分の位置から当てられるかもしれないという欲が出て
どうしても注目してしまいます(経験上ですが)
この時に撃っていない人間がどれだけ情報を与えずに
有利なポジションに付けるかが重要だと思うわけです
まさに「オフ ザ シューティング」?(英語は苦手です)
横道にそれていますが
「連携」というものにも種類があると思っています
・味方を進行させる連携
・相手を倒す連携
・味方への注意をそらす連携
とりあえず三つ書き出しましたが
もう少しあるかもしれません
個々に名前をつけるとすれば
・進行連携
・連携
・陽動連携
とでも言いましょうか
最終目的はフラッグを取ることですが
そのために相手を倒すことが前提となります
各連携の種類も基本的には相手を倒す前提だと思います
種類ごとに解説していこうかと思うのですが
まだ少し固まっていないところもあるので
概略だけ
進行連携:味方が次のポジションに着きたいのだが
相手の射撃や注目度で動けずにいる場合の援護
援護する側は相手の情報取得を封じ(視覚的にはバリに張り付かせる等)
味方を進行させる
この場合フォーメーション的には前後の関係となり
後ろからの援護で前衛が進むイメージ
連携:単独相手に対して味方複数が同時または意図的なズレを作って
攻撃を与える 単独相手に多方向から射撃することで
相手の逃げ場をなくし倒す形
フォーメーション的には横に開く形で
相互の距離感と情報の共有が大事
陽動連携:自分が注目されることで
別エリアへの増援を防いだり
味方の隠密進行を隠したりする形
多数での行動もできる
とまぁ書いてみたんですが
この連携の種類と組み立て方と中間目標が味方と共有してないと
できないものかもしれません
またゲーム中に言葉等では説明しきれないものですので
インスピレーションが似ているか
瞬間瞬間の状況を見極め
それに対応しなければならないわけです
そう言う意味ではものすごく高度なことかもしれません
また気になった時にでも更新したいと思います
寒くて凹みます
今回は少しですがブラインドと連携について考察したい感じです
いつも書いていますが戯言ですので
ご容赦願います
前々回のブログで「ブラインド」なんてしたり顔で書いていますが
基本的には当方が勝手に言っているだけですので
サバイバルゲーム業界全般で使える用語ではありませんのであしからず
情報戦であると仮定している以上
その情報は位置情報であると書きました
情報を得るやり方は過去にも書きましたので
詳しい説明は避けますが
羅列すると
・視覚
・聴覚
ではないでしょうか
細かくすればもっと細分化しますが
細かいと分類しきれませんので
長所と短所についても過去に書いていますので割愛
ポイントとして相手の隠れているバリケードは
相手が当たらないようにするためだけなのか?ということです
「何言ってんだ」って感じですが
バリケードに隠れるというのはもちろん相手からの射撃に対して
当たらないようにするためです
当然ですね
しかしですね
ある一定の距離であれば
実は自分を相手から隠してくれるブラインドになるということです
この感覚は文章にしても伝わらないと思うのですが
意識するとわかるかもしれません
例えばですが
バリケードに相手がいます
自分も相手バリケードから5mのバリケードにいます
相手がバリの左から銃を出してこちらを撃ってきましたので
バリにへばりつき相手の射撃が止むのを待ちます
相手の射撃が止みました
相手の情報を得るためにバリから様子を伺います
相手がいることは確実ですが
相手はバリから顔を出してません
こんな状態があったとします
前提条件としてこの二人以外は周りに人がいないため連携もできませんし
相手の援護も無いとします
この時に相手が隠れているバリケードは
自分にとって相手の目隠しになるということです
先に挙げた情報の取得方法の「視覚」が相手は使えません
この瞬間に移動(有利なポジションに)できないかということです
もちろん例に関して言えば1:1の状況ですので
ゲームで使える状況としては少ないかもしれませんが
フィールドにあるバリや構造物を使い視覚の分断が出来るエリアを認識し味方との連携が
確立すれば実際にはよくある状況なのかもしれません
先ほど書いた例のような状態で
どのように行動するかを考えてみてください
よくありがちなのは相手が顔を出した瞬間狙えるように
自分がバリから狙って待つという戦法ではないでしょうか
もちろん間違っていませんし
うまくイニシアチブがとれているわけで
当方も良くやります
しかし
時間制限のあるゲームということを加味すると
相手が出てくるまで待つというのは
相手側にイニシアチブを取られている可能性もあるわけです
特にゲーム後半であれば逆転を狙うより時間切れを狙う戦術に切り替えてくるでしょう
時間切れであれば勝敗はないわけで引き分けです
そういう意味では相手の戦法にハマっていると言えます
ここで言いたいのは
相手にイニシアチブを取られずに
言い方としてどうかとは思いますが効率的に進行する前提として考えれば
相手の出方を待つには時間がかかりすぎかもしれません
もちろん毎回うまくいくとは限りませんが
膠着というゲームはなくなると思うわけです
前にも書きましたが
この遊びに関しては時間が経てば人数が減ります
人数が減ることでこのような状態も生まれるやすくなるわけです
そして情報の取得が大事だとも書きました
逆を言えばいかに自分の情報を隠すかでもあります
特に「視覚」は情報取得の大きなウエイトを占めていると思っています
だからこそバリにへばりつけばその方向に対して
情報の取得が困難になると考えればいいわけです
これは相手も一緒ですし自分にもあてはまることになるので
どちらがうまく使えるか(イニシアチブが取れるか)ということにつながってくるわけです
ブラインドには色々な方法があると思います
・ある程度の距離があるバリケードや構造物を使う方法
・相手の隠れているバリケードや構造物を使う方法
・フィールドの高低差や死角を使う方法
とりあえず三つ書き出しましたがどれも自分との距離が一定あいていることが重要です
実は自分がバリケードにへばりつく(書き方がいいかわかりませんが)場合には
自分にとっての利がない場合が多い気がします(経験上ですが)
もちろん前提としてバリケードは弾除けです
しかしそれだけでないことが重要だと思うわけです
例えば
相手への射撃牽制をしている間は
相手はバリケードにへばりつきます
その場合相手の視覚情報は0に近くなるわけです
逆にそのような「心理情報」をこちらが取得すれば
有利な位置へ動くことも可能になります
ゲームが情報戦である以上相手に動く瞬間を見られないことは
大きなアドバンテージになると思うわけです
さてここまでブラインドについて書きましたが
これを踏まえたうえで連携を考察する場合どうなるでしょうか?
「連携」と聞くと何を連想しますか
SWATのようなクリアリングでしょうか
当方の経験上では相手を倒すための騙し合いの手段と考えています
サッカーでフォアードがキーパーからゴールを奪うのに壁パスとかスルーしたり
後方からマークしてない人間がゴール前に入ってくる動きを見たことありませんか
サバイバルゲームの連携もあれに近いのではないかと考えています
どういうことかというと
ある意味で陽動ということです
サッカーにしてもボールを持っている人間に注意が行くわけです
そしてゴールを決めるときには
ボールを持っていない人間の動き「オフ ザ ボール」の動きが左右するなんて
解説で聞きますが
ゲームも同じことが言えるのではないでしょうか
鉄砲を撃っている人間はやはり注目を浴びます
なぜなら情報戦と踏まえて
聴覚情報を発信し続けているわけです
しかも実体験上みんなが撃っているときは体のどこかが保護されていないと知っているわけです
そうすると自分の位置から当てられるかもしれないという欲が出て
どうしても注目してしまいます(経験上ですが)
この時に撃っていない人間がどれだけ情報を与えずに
有利なポジションに付けるかが重要だと思うわけです
まさに「オフ ザ シューティング」?(英語は苦手です)
横道にそれていますが
「連携」というものにも種類があると思っています
・味方を進行させる連携
・相手を倒す連携
・味方への注意をそらす連携
とりあえず三つ書き出しましたが
もう少しあるかもしれません
個々に名前をつけるとすれば
・進行連携
・連携
・陽動連携
とでも言いましょうか
最終目的はフラッグを取ることですが
そのために相手を倒すことが前提となります
各連携の種類も基本的には相手を倒す前提だと思います
種類ごとに解説していこうかと思うのですが
まだ少し固まっていないところもあるので
概略だけ
進行連携:味方が次のポジションに着きたいのだが
相手の射撃や注目度で動けずにいる場合の援護
援護する側は相手の情報取得を封じ(視覚的にはバリに張り付かせる等)
味方を進行させる
この場合フォーメーション的には前後の関係となり
後ろからの援護で前衛が進むイメージ
連携:単独相手に対して味方複数が同時または意図的なズレを作って
攻撃を与える 単独相手に多方向から射撃することで
相手の逃げ場をなくし倒す形
フォーメーション的には横に開く形で
相互の距離感と情報の共有が大事
陽動連携:自分が注目されることで
別エリアへの増援を防いだり
味方の隠密進行を隠したりする形
多数での行動もできる
とまぁ書いてみたんですが
この連携の種類と組み立て方と中間目標が味方と共有してないと
できないものかもしれません
またゲーム中に言葉等では説明しきれないものですので
インスピレーションが似ているか
瞬間瞬間の状況を見極め
それに対応しなければならないわけです
そう言う意味ではものすごく高度なことかもしれません
また気になった時にでも更新したいと思います
2012年03月20日
徒然に
ゲーム終わってから
ワイヤートラップで膝を痛打!!!!
久しぶりにびっくりゲロでそうでした
そんなこんなで今回の記事
膝が血だらけ腫れまくり・・・・
ゲーム終わってるとガードしてないですよ
今日は「飛龍」さんにお誘いをうけて
バトルシティ戦でした
前回行ったのはいつのことだろうか・・・
今回の反省
フィールドにいろんなエリアを詰め込んだ
逆に難しいフィールドでした
エリアごとの切り替わりと
そこをケアしつつエリアをまたいでの援護
味方の進行度合いがわからず
また相手の進行もわからないエリアがあるので
情報共有の重要さが際立つ感じでした
前回まとめで少し書きましたが
やはり「ブラインド」という技術が
特に建物の密集地域では活用できそうでしたが
当方ができたかは微妙でした
当方は良くタイミングという言葉をよく使います
難しいので文章にするのをためらっていましたが
ちょっとだけ書いてみたいと思います
ゲームが勝敗を着けるフラッグ戦である以上
前に進むことは前提です
しかし前に進むという行為はそんなに簡単にできるわけじゃないのは
ゲームをしてみるとわかります
よく膠着ゲームと言われますが
前に進む方法がなくなり
ルートを変えてもうまくいかない場合に
当方はなりがちでした
しかし時間制限がある以上
ルートの変更は難しいこともありますし
なにより膠着戦は面白くないです
そこでタイミングです
ここでいうタイミングは前に出るタイミングです
相手の頭を下げ(視覚情報を遮断して)
その刹那の瞬間に今自分がいるところよりも
前に進むことです(相手にとって嫌な位置)
実際にやろうとすると相手がいつ頭(鉄砲)を出すか
わかりませんし
自分の隠れているバリケードの向こう側の情報もわからない
状態ですので
一か八かになりがちですが
そこは五感と味方からの情報を精査して
7:3ぐらいの感覚で
タイミングを見つける感じです
今日も一回成功しましたが
成功すると相手のテリトリーへ進行できるので
相手をびっくりさせることができます
一種の抜けになる感じですね
感覚的なものなので
難しいですが
前回書いた「心理情報」もつかうといいかもしれません
まぁとにもかくにも
楽しいゲーム会でした
「飛龍」の皆様をはじめ参加せれた方々に感謝です
それにしても膝が痛いです・・・
ワイヤートラップで膝を痛打!!!!
久しぶりにびっくりゲロでそうでした
そんなこんなで今回の記事
膝が血だらけ腫れまくり・・・・
ゲーム終わってるとガードしてないですよ
今日は「飛龍」さんにお誘いをうけて
バトルシティ戦でした
前回行ったのはいつのことだろうか・・・
今回の反省
フィールドにいろんなエリアを詰め込んだ
逆に難しいフィールドでした
エリアごとの切り替わりと
そこをケアしつつエリアをまたいでの援護
味方の進行度合いがわからず
また相手の進行もわからないエリアがあるので
情報共有の重要さが際立つ感じでした
前回まとめで少し書きましたが
やはり「ブラインド」という技術が
特に建物の密集地域では活用できそうでしたが
当方ができたかは微妙でした
当方は良くタイミングという言葉をよく使います
難しいので文章にするのをためらっていましたが
ちょっとだけ書いてみたいと思います
ゲームが勝敗を着けるフラッグ戦である以上
前に進むことは前提です
しかし前に進むという行為はそんなに簡単にできるわけじゃないのは
ゲームをしてみるとわかります
よく膠着ゲームと言われますが
前に進む方法がなくなり
ルートを変えてもうまくいかない場合に
当方はなりがちでした
しかし時間制限がある以上
ルートの変更は難しいこともありますし
なにより膠着戦は面白くないです
そこでタイミングです
ここでいうタイミングは前に出るタイミングです
相手の頭を下げ(視覚情報を遮断して)
その刹那の瞬間に今自分がいるところよりも
前に進むことです(相手にとって嫌な位置)
実際にやろうとすると相手がいつ頭(鉄砲)を出すか
わかりませんし
自分の隠れているバリケードの向こう側の情報もわからない
状態ですので
一か八かになりがちですが
そこは五感と味方からの情報を精査して
7:3ぐらいの感覚で
タイミングを見つける感じです
今日も一回成功しましたが
成功すると相手のテリトリーへ進行できるので
相手をびっくりさせることができます
一種の抜けになる感じですね
感覚的なものなので
難しいですが
前回書いた「心理情報」もつかうといいかもしれません
まぁとにもかくにも
楽しいゲーム会でした
「飛龍」の皆様をはじめ参加せれた方々に感謝です
それにしても膝が痛いです・・・
2012年03月16日
徒然に
だらだら始めたブログですけど
相当記事もたまりましたし
そんな訳でちょっとマトメ
現時点で当方の考えてることです
参考になるかはわかりませんし
批判もあると思いますが まぁ個人的な戯言ですので
ご容赦です
サバイバルゲームを勝敗のあるゲームとして捉えれば
勝敗を分けるポイントが必ずあると考えてます
そのポイントをいかに意図的に作るかが問題だと思っています
もちろん状況や味方の人数等の条件でポイントは変わってくると
思います
しかしある意味一本筋のある考え方を明示してあとは
どう生かしていくかだと思うわけです
このブログで大前提としている
「ゲームは情報戦」
「兵は鬼道なり」
まずはこの説明から復習しようと思います
まず「ゲームは情報戦」から
サバイバルゲーム(以下ゲーム)はその動きのほとんどを
相手に見つからないようにします
なぜか?それは見つかると撃たれて自チームの人数が減るというルールのためです
そのため自分の位置情報をできるだけ相手に見つかりたくないという心理状況になります
逆に言えば
相手の位置情報をより多く正確に得ることができれば有利にゲームを進められるということです
またランチェスターの定理から
統計学上は3対1の人数差であれば損害を最低限に出来ることになります
そうすると相手の位置情報を最低3人正確に把握し同じ相手に攻撃を加えることで
損害を出さずに打撃を与えられます(計算上ですので上手くはいかないと思いますが・・・)
ここで問題なのは情報の共有化です
そうは言っても難しいことなのですが
意識することで連携や援護が格段に違います(当方経験上ですが・・)
上記で書いたのは位置情報についてです
今度はもっと細かい情報です いい言い方がないので
「心理情報」とでも言いましょうか
対相手(単独)の今現在の状況を得られる情報から推測する感じです
例えば
※バリケードの裏に居ることはわかっています
しかし顔を出しません
チラチラ向かって左から銃口がみえます またバリケードの左側から影も見えてます
こんな状況があったとします
この場合相手の位置を推測するとすれば
バリケード裏の向かって左側に位置して左側を狙っている(銃口が左を向いている)となるわけです
もし単独で攻める場合
右から回り込む攻め方が一番リスクが少ないのではないでしょうか
このように隠れている相手がどちらを向きどちらに注意を向けているのか
これを推測し対応していくわけです
文章では単独の場合で書きましたが
この情報を共有すればセル単位での攻め方(リスクの少ない)ができると思うのです
そしてもう一つ
味方の情報というものがあります
ここの情報もあくまでも位置情報と心理情報です
味方の撃ってる方向から相手の位置を予測したり
なんども振り返れば援護が欲しいのかもしれません
連携するにしても援護するにしても味方の位置が分からなければできませんし
そこから読み取れる相手の情報もあるわけです
情報についてまとめると
1、相手の位置情報の取得・共有化
2、味方の位置情報の取得
3、上記を利用しさらに相手心理情報を推測し攻撃
となるわけです
1と2はフィールドの範囲として大きな情報で
3はフィールドの範囲として小さな情報です
簡単に書いていますが
実際に共有化というのは難しい問題です
フィールドの各エリアの名称についてもチームごとまたは個人ごとに違いがあり
声を出すのか 無線を使うのか ハンドサインで伝えるのか
伝達手段についてもいろんなケースがあるわけです
上記であげた3つの伝達手段の選択する条件を少し羅列しますが
絶対でなく状況状況に応じて変わることはありますので参考程度に
考えてください
声を出す:一番ポピュラーですが一番しにくい伝達手段(相手に見つかるため)です
しかし当方は基本だと思います
声を出すことで一度で聞こえる範囲全てに伝達でき
相手にも聞こえるということです
特に相手の位置情報は声を出すことで相手にプレッシャーを与えます
経験上当方の位置情報を声で出された場合進行速度は遅くなり
動きづらくなります これは相手に全て筒抜けになっているのかもしれないという
プレッシャーによることが大きいです
ただし見つかってしまう確率は段違いであがります
無線を使う:ここ最近増えてきた手段です
ただある程度の慣れと技術が必要です 最初の一瞬のズレや聞き取りづらい場合等
不安要素もある方法です
しかし相手に聞かれないということは
味方同士のタイミング合わせや進行ルートの変更等チーム内での動きに
特化していると思います
ハンドサインを使う:極近距離の味方との連絡で使える手段です
特別なルールや慣れが必要で3つの中では一番難しいかもしれません
しかし極近距離で相手がいる場合や小声でも位置バレするような場合には
一番いい方法かもしれません
ただし味方が常に意識している状況で
アイコンタクト(経験上ですが)が出来てる状態でないと
伝わらなかったりルールをしっかり設定して習得してないと
使えない高度な方法です
ここまで書いたとおり
ゲームのルール上(フラッグ戦や全滅戦ですが・・・)
時間に応じて人数の減るルールが前提ですので
味方の損害を減らし相手の人数を減らすかが
ゲームの構築の第一歩だと思います
その手段を選択するためにも情報というものが大切になるわけです
そして逆をいえばいかに相手に自分の位置情報を与えないかが
重要になるわけです
当方経験上相手を見つけるのは相手が動いている場合が多いです
ということは動かなければ見つからないわけです
しかし勝利にも繋がらない訳ですので
動くことをしつつ見つからない技術も必要になります
細かくは文章化できませんが
相手と自分との間に構造体を入れることで
視覚の分断を作るわけです
分断されている時間は相手には見えていないわけで
うまく活用すれば位置情報を遮断できるわけです
当方は「ブラインド」と呼んでいます
もちろんこれも一長一短で
相手が見えないということは自分も見えないということなので
逆にこの分断時間を相手に使われることもあるわけです
「兵は鬼道なり」
これは孫子で出てくる言葉です
すごく簡単に言えば「戦いは騙し合いである」という感じでしょうか
ここでいう騙し合いにしても
根底にあるのは相手の情報です
特に上で言っている「心理情報」というものです
この心理情報をうまくつかんで攻撃につなげる場合と
心理情報をうまく流して迎撃する場合この二つになると思います
あいていにいえば陽動です
実は個人技的な技術でも全てにおいて陽動が存在すると感じています
「走る」「隠れる」「撃つ」
とりあえず個人での技術を三つ書き出しましたが
ここでも陽動は使われています
走る:上にも書きましたがブラインドで情報を遮断することも陽動でしょう
あるいは先行潜伏する攻め方もある意味陽動です
走ることで相手に注目されやすいということは
味方のマークが外れる確率が上がるということです
これも味方の進行に対する陽動かもしれません
隠れる:入ったバリケードから相手にバレないように他に移るという陽動があります
これもブラインドを使うと効果的かつ楽にできるかもしれません
撃つ:当方は目線は撃つ相手を見ながら顔を逆に向けることがあります
相手が「心理情報」を読み取る際顔の向きで判断されることがありますので
そこを読み取らせず行動することは陽動を使っているのかもしれません
実際のゲームでは大小様々な陽動で成り立っていると感じています
ここに羅列すればキリがないのでしませんが
前提として考えることは
相手の意表を突く動きです
上の方で書いている※印の例の場合でも相手の意識が左に向いていることを前提として
考えれば相手は自分の右から攻めてくる想定で待っています
この想定を読み取り相手の左から攻めることで相手の意表を突けるわけです
(もちろんこんなに簡単ではないでしょうが・・・)
さらにもっと相手の意識を左に寄せるには
左側に撃ち込むことで心理的なパニックを起こさせれば
もっと効率的ですしこれを二人でやれば
連携で倒す方法となるわけです
(後で書きますが連携という概念も曖昧すぎて整理したほうがいいと思いますけど)
この騙し合いで非常に重要なファクターとして
イニシアチブがあります
あっているかわかりませんが主導権ですね
刹那刹那で主導権がどこにあるのかを見極めることが
相手をうまく陽動に持ち込める大きなファクターになっているように
感じます
実際には意識せずにみんながやっていることですが
意識することで断然違いが出てきます
そしてここで勘違いしないで欲しいのは
主導権がないから劣勢とかあるから優勢というわけでなく
主導権を握りかつ意表をつく動きができて
初めて意味のあるものになります
例えば主導権が握れない場合でも
「待ち」という戦術を選択すれば
主導権が握れなくてもうまくいくことがあるわけです
ちょっとここで過去の記事の引用を
【サバイバルゲームの「基礎常識」】
1 1対1という状況
1対1という状況は、なかなかありえない状況ではあるが、個人技という観点では、重要な意味を持つ。
お互いを認識している場合、どのようにイニシアチブをとるかが重要である。
対策例
①相手の頭を、下げさせて次に出てくるのを狙って待つ
②相手の頭が下がった瞬間、有利なポジションにつく
どちらの方法も、相手の視覚をさえぎる(情報を与えない)ことでイニシアチブをとる方法である。
イニシアチブをとる=視覚をさえぎる=個人技があるともいえるかもしれない
また②の有利なポジションも曲者である
相手の対して有利なポジションとはなんなのか?
単純な話「右利き」が、多いということは相手の左から攻めるほうが有効である。
(バリケードから相手が撃つ場合を想定すると左に銃を向けるとバリに当たるから)
また縦の動きより横の動きのほうが狙いずらい
相手の周囲の状況を想像して、相手が身を隠す場所のない方向
2 2マンセルという動き
2マンセルというユニットがある。
この場合の、動き方を考えてみる。
SWAT等の話は除外し ゲームのみで考える
あくまでも相手を倒す攻勢のユニットであるべきなので
前衛 後衛という役割になるだろう。
単純に完全に縦に並ぶことはリスクが大きいので避けるべきである。
①前衛の役割
相手に気づかれず近づき倒すことができれば一番いい
相手の位置情報を収集し 倒すべき相手を決めてそこに近づく
気づかれないための方法として
自分が動く瞬間に発見される確率が高いので相手が撃っているときや
頭の下がった瞬間 相手の目線の方向を確認して見てない瞬間に動く
また バリケードの位置をうまく使い相手の死角を利用することも重要(ブラインドの技術)
②後衛の役割
まず遠距離から相手を倒すor牽制することが重要
そして自分が決して当たらないようにする
また前衛の動きがばれないよう自分に注意を引き付ける
相手の位置情報を前衛に伝える 前衛が動きやすいように相手の頭を下げる
前衛と敵との距離を考えたポジショニングを心がける
連携というよりは、お互いの動きを利用して相手を倒す形が望ましい
前衛は後衛の射撃音を利用して情報を収集して相手の位置を確認して
後衛は前衛の位置を考えながら位置を移動する(クロスファイヤ)
前衛が気づかれた場合、後衛は自分の位置を変えて有利なポジションに移動する
後衛は最終ラインになることもあるので 最悪の場合は前衛を見捨てる
前衛 後衛は役割をチェンジする(追い抜くことで役割を交換する)ことも可能である
3チーム戦術
あえてサッカーで言えば
①ラインの上げ下げ
②サイドからの攻撃
③楔の位置への進行
①ラインの上げ下げ
ラインとは絶対安全圏
相手が進行していないスペースで味方が保持しているスペース
このスペースをいかに多く取るかが重要である
このスペースが広ければ、相手の進行に対しての処理や味方の逃げ場として活用
交戦スペースが小さくなるので位置把握や情報の確実性も増し索敵範囲も狭くなる
牽制射撃や狙い撃ちも確率が上がる
またこのスペースのみ索敵しなくてもよいスペースとなる
ただし広すぎるスペースの場合 相手のカウンター(隠密進行)を逃す場合もあるので
チーム全体で意識的に分割したスペースを確認する
②サイドからの攻撃
サイドというよりエンドラインからの進行をさす
エンドライン際は索敵範囲が狭いため進行しやすい
ライン際にいる人間は多くのスペースを確認or索敵しやすいため
交戦スペースに対して横槍を入れやすい
フラッグダッシュ時に第二陣となることや 本隊との合流など
あらゆる状況に対して有利なポジションとなる
③楔の位置
相手のラインよりも進行した位置(相手の絶対安全圏)に一人でも進行できれば
相手を挟み撃ちのできる
味方との同士討ちの危険性もあるが、非常に有利なポジションである
交戦スペースとは
味方と敵が交戦しあい 勝敗に確実性のないスペース
例 バリケード同士で撃ち合い移動もできず互いに次の手が出しにくい状況
ゲームではこの交戦スペースが最大で味方の人数だけ生まれる
Aスペース(1対1と仮定)Bスペース(1対1と仮定)と生まれた場合
Aの味方がAの敵と撃ち合いしつつBの敵に横槍を入れる形で2対1の状況を作り出して
勝率を上げるのが「プレート理論」である
これに必要なのは 打ち合いをしつつ 周囲の状況を見渡せる広い視野と絶好のポジションへの移動
味方同士での意思疎通が不可欠である
また ラインからの適切な指示等で行うことも考えられる(森林フィールドでは難しいが・・
4速攻と遅攻
スタート時に最初の撃ち合い(前線ライン)がフィールドのどの辺り
で行われるかにより速攻と遅攻に分かれる
前線ラインをフィールドセンターより相手側に設けることができれば速攻となり
フィールドセンターより自陣に近ければ遅攻となる
また位置ではなく時間的な速攻と遅攻もある
どちらも相手との会敵位置を把握することができないとむずかしい
フィールドセンターとは
距離的な中央でなく統計的に前線となりやすいラインのこと
進行のしやすさや障害物によりフィールドによってさまざまであると考えられる
①速攻
相手の出鼻をくじき 相手のポジショニングよりも早い段階で交戦を始めるので
建て直しの困難な状況を作り出す また崩れたところにそのまま進行すれば楔の形になり
有利に進めることができる
ただし 相手の進行が早く味方の前線ラインが崩れたときは防戦になるので注意が必要
また 味方のラインも状況により上げないと 前衛と後衛の間にスペースが生まれ不利な状況に
なることも考えられるので 後衛もラインを上げなければならない
②遅攻
相手のポジショニングを確認しつつ 進行し確認した相手を倒しつつ
徐々に前線ラインを上げていく
この場合 相手の位置は確認しているが 味方の位置もばれているので
遠距離戦になりやすい
フリーな味方(隠密)をつくり その味方とのツーマンセルの動きにより
相手を排除していく組み立て方がよい
ただし フリーを落とされると 動けなくなり(数的不利もまねく)膠着あるいは
敗戦となりやすい
5スタートダッシュの重要性
ゲーム開始時にスタートダッシュするほうがイニシアチブを取りやすい
ただしチームとして連携を意識した場合 多少の決め事は必要である
①前衛
前衛と呼ばれるポジションは誰よりも何よりも早く
フィールドセンターよりも相手側に近づくことが最重要である
意識的に相手の目に入らないラインや一時的にでも視覚に入らないラインを使い
とにかく近づく
到達地点についてからは相手への発砲も控えまず状況把握を優先する
味方の声 無線? 周囲状況 銃声 足音 索敵 により
自身が気づかれていないのか?を確認する
②後衛
後衛と呼ばれるポジションは前衛に気が回らないように
相手に対して発砲し声を出し威嚇する
そのときにできればフィールドセンターより前(奥?)で相手の足を止める
この場合意識的に前衛と後衛の間のゾーンを空けて
後衛の位置が最前線であると錯覚させる
前衛がポジショニングした場合
相手の位置情報を与えつつ前衛位置とクロスになる位置に移動し
前衛の動きに対してラインを上げていく
とまあ自分で過去に書いた記事ですが
これだけ読んでも上手くはいかないと思います
補足的に
援護という行為
援護とはとにかく撃つことですと書くと怒られそうですが
援護の目的とは
・味方に意識している相手を自分の方に意識を向けさせる
・最初に書いた相手の「心理情報」を狭くして味方の攻撃のタイミングを作る
という感じではないでしょうか
書き方は2種類ですが同じことを書いてる気がします
撃たれれば反応します それは当たらない弾であっても
心理的なプレッシャーを与えられるわけです
プレッシャーは判断を鈍らせます
特にバリケードへの射撃は着弾音が多ければ多いほど
プレッシャーは高まりますし情報取得を困難にします
☆目線を上げれば当たるし着弾音で音も聞こえないとなれば
そこでうずくまるか後方に下がるか
この状態にすることが援護であり
この状態であれば近づいていくことも容易になります(経験上ですが)
ある意味味方が自由に動けるスペースを(短時間・狭い範囲)で作り出す感じですね
それには撃つことが重要です
昨今では弾数制限もありますしセミ縛りもありますが
基本の援護はこれだと思います
崩す動き
味方が援護をしている場合☆の状況で動き出せるかどうかです
倒すために近づく・回り込む動きが崩す動きだと思います
また相手が下がった瞬間に合わせて自分が前に出て
距離を開かせないのも重要です
この行為は自分の持っている情報を途切れさせないためです
当方の経験ですが下がった相手と相対した場合相手の位置を見失うと
索敵から始めなければなりません
しかし下がった瞬間に距離を詰めることで
相手の位置情報の空白を作らず
攻めることができるわけです もちろん味方に援護(相手の情報収集を邪魔する)はしてもらいますが
進行ルートの決め方
崩す動きで崩せれば圧力をかけるわけです
ここでの圧力は数です
残っている味方を集中しどんどん圧力を上げていくわけです
圧力が掛かり相手が圧力ルートに助けに入れば
手薄なルートができるわけで
崩しやすく結果的に進行しやすくなるわけです
集団での陽動
進行ルートでも書いてますが圧力をかければ
相手は増援します
増援するということはどこかに綻びができるわけです
このタイミングで進行すれば陽動になります
フラッグアタックの仕方
相手が残っている場合でもフラッグアタックは
人数をかけたほうが確率が高いと思います
フラックアタックするタイミング合わせ
各々別ルートから一斉にアタックすることで
確率を上げるわけです
細かいこともいえば膨大な記事はかけますが
言葉にするのは難しいこともありますので
今回はここまでにします
相当記事もたまりましたし
そんな訳でちょっとマトメ
現時点で当方の考えてることです
参考になるかはわかりませんし
批判もあると思いますが まぁ個人的な戯言ですので
ご容赦です
サバイバルゲームを勝敗のあるゲームとして捉えれば
勝敗を分けるポイントが必ずあると考えてます
そのポイントをいかに意図的に作るかが問題だと思っています
もちろん状況や味方の人数等の条件でポイントは変わってくると
思います
しかしある意味一本筋のある考え方を明示してあとは
どう生かしていくかだと思うわけです
このブログで大前提としている
「ゲームは情報戦」
「兵は鬼道なり」
まずはこの説明から復習しようと思います
まず「ゲームは情報戦」から
サバイバルゲーム(以下ゲーム)はその動きのほとんどを
相手に見つからないようにします
なぜか?それは見つかると撃たれて自チームの人数が減るというルールのためです
そのため自分の位置情報をできるだけ相手に見つかりたくないという心理状況になります
逆に言えば
相手の位置情報をより多く正確に得ることができれば有利にゲームを進められるということです
またランチェスターの定理から
統計学上は3対1の人数差であれば損害を最低限に出来ることになります
そうすると相手の位置情報を最低3人正確に把握し同じ相手に攻撃を加えることで
損害を出さずに打撃を与えられます(計算上ですので上手くはいかないと思いますが・・・)
ここで問題なのは情報の共有化です
そうは言っても難しいことなのですが
意識することで連携や援護が格段に違います(当方経験上ですが・・)
上記で書いたのは位置情報についてです
今度はもっと細かい情報です いい言い方がないので
「心理情報」とでも言いましょうか
対相手(単独)の今現在の状況を得られる情報から推測する感じです
例えば
※バリケードの裏に居ることはわかっています
しかし顔を出しません
チラチラ向かって左から銃口がみえます またバリケードの左側から影も見えてます
こんな状況があったとします
この場合相手の位置を推測するとすれば
バリケード裏の向かって左側に位置して左側を狙っている(銃口が左を向いている)となるわけです
もし単独で攻める場合
右から回り込む攻め方が一番リスクが少ないのではないでしょうか
このように隠れている相手がどちらを向きどちらに注意を向けているのか
これを推測し対応していくわけです
文章では単独の場合で書きましたが
この情報を共有すればセル単位での攻め方(リスクの少ない)ができると思うのです
そしてもう一つ
味方の情報というものがあります
ここの情報もあくまでも位置情報と心理情報です
味方の撃ってる方向から相手の位置を予測したり
なんども振り返れば援護が欲しいのかもしれません
連携するにしても援護するにしても味方の位置が分からなければできませんし
そこから読み取れる相手の情報もあるわけです
情報についてまとめると
1、相手の位置情報の取得・共有化
2、味方の位置情報の取得
3、上記を利用しさらに相手心理情報を推測し攻撃
となるわけです
1と2はフィールドの範囲として大きな情報で
3はフィールドの範囲として小さな情報です
簡単に書いていますが
実際に共有化というのは難しい問題です
フィールドの各エリアの名称についてもチームごとまたは個人ごとに違いがあり
声を出すのか 無線を使うのか ハンドサインで伝えるのか
伝達手段についてもいろんなケースがあるわけです
上記であげた3つの伝達手段の選択する条件を少し羅列しますが
絶対でなく状況状況に応じて変わることはありますので参考程度に
考えてください
声を出す:一番ポピュラーですが一番しにくい伝達手段(相手に見つかるため)です
しかし当方は基本だと思います
声を出すことで一度で聞こえる範囲全てに伝達でき
相手にも聞こえるということです
特に相手の位置情報は声を出すことで相手にプレッシャーを与えます
経験上当方の位置情報を声で出された場合進行速度は遅くなり
動きづらくなります これは相手に全て筒抜けになっているのかもしれないという
プレッシャーによることが大きいです
ただし見つかってしまう確率は段違いであがります
無線を使う:ここ最近増えてきた手段です
ただある程度の慣れと技術が必要です 最初の一瞬のズレや聞き取りづらい場合等
不安要素もある方法です
しかし相手に聞かれないということは
味方同士のタイミング合わせや進行ルートの変更等チーム内での動きに
特化していると思います
ハンドサインを使う:極近距離の味方との連絡で使える手段です
特別なルールや慣れが必要で3つの中では一番難しいかもしれません
しかし極近距離で相手がいる場合や小声でも位置バレするような場合には
一番いい方法かもしれません
ただし味方が常に意識している状況で
アイコンタクト(経験上ですが)が出来てる状態でないと
伝わらなかったりルールをしっかり設定して習得してないと
使えない高度な方法です
ここまで書いたとおり
ゲームのルール上(フラッグ戦や全滅戦ですが・・・)
時間に応じて人数の減るルールが前提ですので
味方の損害を減らし相手の人数を減らすかが
ゲームの構築の第一歩だと思います
その手段を選択するためにも情報というものが大切になるわけです
そして逆をいえばいかに相手に自分の位置情報を与えないかが
重要になるわけです
当方経験上相手を見つけるのは相手が動いている場合が多いです
ということは動かなければ見つからないわけです
しかし勝利にも繋がらない訳ですので
動くことをしつつ見つからない技術も必要になります
細かくは文章化できませんが
相手と自分との間に構造体を入れることで
視覚の分断を作るわけです
分断されている時間は相手には見えていないわけで
うまく活用すれば位置情報を遮断できるわけです
当方は「ブラインド」と呼んでいます
もちろんこれも一長一短で
相手が見えないということは自分も見えないということなので
逆にこの分断時間を相手に使われることもあるわけです
「兵は鬼道なり」
これは孫子で出てくる言葉です
すごく簡単に言えば「戦いは騙し合いである」という感じでしょうか
ここでいう騙し合いにしても
根底にあるのは相手の情報です
特に上で言っている「心理情報」というものです
この心理情報をうまくつかんで攻撃につなげる場合と
心理情報をうまく流して迎撃する場合この二つになると思います
あいていにいえば陽動です
実は個人技的な技術でも全てにおいて陽動が存在すると感じています
「走る」「隠れる」「撃つ」
とりあえず個人での技術を三つ書き出しましたが
ここでも陽動は使われています
走る:上にも書きましたがブラインドで情報を遮断することも陽動でしょう
あるいは先行潜伏する攻め方もある意味陽動です
走ることで相手に注目されやすいということは
味方のマークが外れる確率が上がるということです
これも味方の進行に対する陽動かもしれません
隠れる:入ったバリケードから相手にバレないように他に移るという陽動があります
これもブラインドを使うと効果的かつ楽にできるかもしれません
撃つ:当方は目線は撃つ相手を見ながら顔を逆に向けることがあります
相手が「心理情報」を読み取る際顔の向きで判断されることがありますので
そこを読み取らせず行動することは陽動を使っているのかもしれません
実際のゲームでは大小様々な陽動で成り立っていると感じています
ここに羅列すればキリがないのでしませんが
前提として考えることは
相手の意表を突く動きです
上の方で書いている※印の例の場合でも相手の意識が左に向いていることを前提として
考えれば相手は自分の右から攻めてくる想定で待っています
この想定を読み取り相手の左から攻めることで相手の意表を突けるわけです
(もちろんこんなに簡単ではないでしょうが・・・)
さらにもっと相手の意識を左に寄せるには
左側に撃ち込むことで心理的なパニックを起こさせれば
もっと効率的ですしこれを二人でやれば
連携で倒す方法となるわけです
(後で書きますが連携という概念も曖昧すぎて整理したほうがいいと思いますけど)
この騙し合いで非常に重要なファクターとして
イニシアチブがあります
あっているかわかりませんが主導権ですね
刹那刹那で主導権がどこにあるのかを見極めることが
相手をうまく陽動に持ち込める大きなファクターになっているように
感じます
実際には意識せずにみんながやっていることですが
意識することで断然違いが出てきます
そしてここで勘違いしないで欲しいのは
主導権がないから劣勢とかあるから優勢というわけでなく
主導権を握りかつ意表をつく動きができて
初めて意味のあるものになります
例えば主導権が握れない場合でも
「待ち」という戦術を選択すれば
主導権が握れなくてもうまくいくことがあるわけです
ちょっとここで過去の記事の引用を
【サバイバルゲームの「基礎常識」】
1 1対1という状況
1対1という状況は、なかなかありえない状況ではあるが、個人技という観点では、重要な意味を持つ。
お互いを認識している場合、どのようにイニシアチブをとるかが重要である。
対策例
①相手の頭を、下げさせて次に出てくるのを狙って待つ
②相手の頭が下がった瞬間、有利なポジションにつく
どちらの方法も、相手の視覚をさえぎる(情報を与えない)ことでイニシアチブをとる方法である。
イニシアチブをとる=視覚をさえぎる=個人技があるともいえるかもしれない
また②の有利なポジションも曲者である
相手の対して有利なポジションとはなんなのか?
単純な話「右利き」が、多いということは相手の左から攻めるほうが有効である。
(バリケードから相手が撃つ場合を想定すると左に銃を向けるとバリに当たるから)
また縦の動きより横の動きのほうが狙いずらい
相手の周囲の状況を想像して、相手が身を隠す場所のない方向
2 2マンセルという動き
2マンセルというユニットがある。
この場合の、動き方を考えてみる。
SWAT等の話は除外し ゲームのみで考える
あくまでも相手を倒す攻勢のユニットであるべきなので
前衛 後衛という役割になるだろう。
単純に完全に縦に並ぶことはリスクが大きいので避けるべきである。
①前衛の役割
相手に気づかれず近づき倒すことができれば一番いい
相手の位置情報を収集し 倒すべき相手を決めてそこに近づく
気づかれないための方法として
自分が動く瞬間に発見される確率が高いので相手が撃っているときや
頭の下がった瞬間 相手の目線の方向を確認して見てない瞬間に動く
また バリケードの位置をうまく使い相手の死角を利用することも重要(ブラインドの技術)
②後衛の役割
まず遠距離から相手を倒すor牽制することが重要
そして自分が決して当たらないようにする
また前衛の動きがばれないよう自分に注意を引き付ける
相手の位置情報を前衛に伝える 前衛が動きやすいように相手の頭を下げる
前衛と敵との距離を考えたポジショニングを心がける
連携というよりは、お互いの動きを利用して相手を倒す形が望ましい
前衛は後衛の射撃音を利用して情報を収集して相手の位置を確認して
後衛は前衛の位置を考えながら位置を移動する(クロスファイヤ)
前衛が気づかれた場合、後衛は自分の位置を変えて有利なポジションに移動する
後衛は最終ラインになることもあるので 最悪の場合は前衛を見捨てる
前衛 後衛は役割をチェンジする(追い抜くことで役割を交換する)ことも可能である
3チーム戦術
あえてサッカーで言えば
①ラインの上げ下げ
②サイドからの攻撃
③楔の位置への進行
①ラインの上げ下げ
ラインとは絶対安全圏
相手が進行していないスペースで味方が保持しているスペース
このスペースをいかに多く取るかが重要である
このスペースが広ければ、相手の進行に対しての処理や味方の逃げ場として活用
交戦スペースが小さくなるので位置把握や情報の確実性も増し索敵範囲も狭くなる
牽制射撃や狙い撃ちも確率が上がる
またこのスペースのみ索敵しなくてもよいスペースとなる
ただし広すぎるスペースの場合 相手のカウンター(隠密進行)を逃す場合もあるので
チーム全体で意識的に分割したスペースを確認する
②サイドからの攻撃
サイドというよりエンドラインからの進行をさす
エンドライン際は索敵範囲が狭いため進行しやすい
ライン際にいる人間は多くのスペースを確認or索敵しやすいため
交戦スペースに対して横槍を入れやすい
フラッグダッシュ時に第二陣となることや 本隊との合流など
あらゆる状況に対して有利なポジションとなる
③楔の位置
相手のラインよりも進行した位置(相手の絶対安全圏)に一人でも進行できれば
相手を挟み撃ちのできる
味方との同士討ちの危険性もあるが、非常に有利なポジションである
交戦スペースとは
味方と敵が交戦しあい 勝敗に確実性のないスペース
例 バリケード同士で撃ち合い移動もできず互いに次の手が出しにくい状況
Aスペース(1対1と仮定)Bスペース(1対1と仮定)と生まれた場合
Aの味方がAの敵と撃ち合いしつつBの敵に横槍を入れる形で2対1の状況を作り出して
勝率を上げるのが「プレート理論」である
これに必要なのは 打ち合いをしつつ 周囲の状況を見渡せる広い視野と絶好のポジションへの移動
味方同士での意思疎通が不可欠である
また ラインからの適切な指示等で行うことも考えられる(森林フィールドでは難しいが・・
4速攻と遅攻
スタート時に最初の撃ち合い(前線ライン)がフィールドのどの辺り
で行われるかにより速攻と遅攻に分かれる
前線ラインをフィールドセンターより相手側に設けることができれば速攻となり
フィールドセンターより自陣に近ければ遅攻となる
また位置ではなく時間的な速攻と遅攻もある
どちらも相手との会敵位置を把握することができないとむずかしい
フィールドセンターとは
距離的な中央でなく統計的に前線となりやすいラインのこと
進行のしやすさや障害物によりフィールドによってさまざまであると考えられる
①速攻
相手の出鼻をくじき 相手のポジショニングよりも早い段階で交戦を始めるので
建て直しの困難な状況を作り出す また崩れたところにそのまま進行すれば楔の形になり
有利に進めることができる
ただし 相手の進行が早く味方の前線ラインが崩れたときは防戦になるので注意が必要
また 味方のラインも状況により上げないと 前衛と後衛の間にスペースが生まれ不利な状況に
なることも考えられるので 後衛もラインを上げなければならない
②遅攻
相手のポジショニングを確認しつつ 進行し確認した相手を倒しつつ
徐々に前線ラインを上げていく
この場合 相手の位置は確認しているが 味方の位置もばれているので
遠距離戦になりやすい
フリーな味方(隠密)をつくり その味方とのツーマンセルの動きにより
相手を排除していく組み立て方がよい
ただし フリーを落とされると 動けなくなり(数的不利もまねく)膠着あるいは
敗戦となりやすい
5スタートダッシュの重要性
ゲーム開始時にスタートダッシュするほうがイニシアチブを取りやすい
ただしチームとして連携を意識した場合 多少の決め事は必要である
①前衛
前衛と呼ばれるポジションは誰よりも何よりも早く
フィールドセンターよりも相手側に近づくことが最重要である
意識的に相手の目に入らないラインや一時的にでも視覚に入らないラインを使い
とにかく近づく
到達地点についてからは相手への発砲も控えまず状況把握を優先する
味方の声 無線? 周囲状況 銃声 足音 索敵 により
自身が気づかれていないのか?を確認する
②後衛
後衛と呼ばれるポジションは前衛に気が回らないように
相手に対して発砲し声を出し威嚇する
そのときにできればフィールドセンターより前(奥?)で相手の足を止める
この場合意識的に前衛と後衛の間のゾーンを空けて
後衛の位置が最前線であると錯覚させる
前衛がポジショニングした場合
相手の位置情報を与えつつ前衛位置とクロスになる位置に移動し
前衛の動きに対してラインを上げていく
とまあ自分で過去に書いた記事ですが
これだけ読んでも上手くはいかないと思います
補足的に
援護という行為
援護とはとにかく撃つことですと書くと怒られそうですが
援護の目的とは
・味方に意識している相手を自分の方に意識を向けさせる
・最初に書いた相手の「心理情報」を狭くして味方の攻撃のタイミングを作る
という感じではないでしょうか
書き方は2種類ですが同じことを書いてる気がします
撃たれれば反応します それは当たらない弾であっても
心理的なプレッシャーを与えられるわけです
プレッシャーは判断を鈍らせます
特にバリケードへの射撃は着弾音が多ければ多いほど
プレッシャーは高まりますし情報取得を困難にします
☆目線を上げれば当たるし着弾音で音も聞こえないとなれば
そこでうずくまるか後方に下がるか
この状態にすることが援護であり
この状態であれば近づいていくことも容易になります(経験上ですが)
ある意味味方が自由に動けるスペースを(短時間・狭い範囲)で作り出す感じですね
それには撃つことが重要です
昨今では弾数制限もありますしセミ縛りもありますが
基本の援護はこれだと思います
崩す動き
味方が援護をしている場合☆の状況で動き出せるかどうかです
倒すために近づく・回り込む動きが崩す動きだと思います
また相手が下がった瞬間に合わせて自分が前に出て
距離を開かせないのも重要です
この行為は自分の持っている情報を途切れさせないためです
当方の経験ですが下がった相手と相対した場合相手の位置を見失うと
索敵から始めなければなりません
しかし下がった瞬間に距離を詰めることで
相手の位置情報の空白を作らず
攻めることができるわけです もちろん味方に援護(相手の情報収集を邪魔する)はしてもらいますが
進行ルートの決め方
崩す動きで崩せれば圧力をかけるわけです
ここでの圧力は数です
残っている味方を集中しどんどん圧力を上げていくわけです
圧力が掛かり相手が圧力ルートに助けに入れば
手薄なルートができるわけで
崩しやすく結果的に進行しやすくなるわけです
集団での陽動
進行ルートでも書いてますが圧力をかければ
相手は増援します
増援するということはどこかに綻びができるわけです
このタイミングで進行すれば陽動になります
フラッグアタックの仕方
相手が残っている場合でもフラッグアタックは
人数をかけたほうが確率が高いと思います
フラックアタックするタイミング合わせ
各々別ルートから一斉にアタックすることで
確率を上げるわけです
細かいこともいえば膨大な記事はかけますが
言葉にするのは難しいこともありますので
今回はここまでにします
2012年03月11日
徒然に
今日は「飛龍」さんを迎えてのTTFゲームでした
今回の反省
いやはやもう難しすぎ
こちらの裏をかく戦術や
なんやかんやでうまくいかないです
いいところがあまりなかったです
原因としては
先行での位置どりを選択してた部分もありますが
読まれ過ぎの部分もあります
まぁしょうがないと言えばしょうがないのですが・・・・
ラインでの統率を諦め
エリア毎の進行に決めました
いろいろ理由はあったのですが
思ったようにはいかないわけで
うーん といった感じ
位置どりと崩し方まぁいろいろ考えるべきですね
ちょっと疲れました
勝敗的には
甲乙つけがたい感じでしたが
個人的には負けた感が強いです
思えば初めて「飛龍」さんと対戦した約一週間後でした
おこがましいので言える立場でないですが
今日あの時間に鳴った防災放送のサイレンを聞いていて
少し厳かになったのも事実です
いろんな出会いを大切にしたいと
感じる一日でした
今回の反省
いやはやもう難しすぎ
こちらの裏をかく戦術や
なんやかんやでうまくいかないです
いいところがあまりなかったです
原因としては
先行での位置どりを選択してた部分もありますが
読まれ過ぎの部分もあります
まぁしょうがないと言えばしょうがないのですが・・・・
ラインでの統率を諦め
エリア毎の進行に決めました
いろいろ理由はあったのですが
思ったようにはいかないわけで
うーん といった感じ
位置どりと崩し方まぁいろいろ考えるべきですね
ちょっと疲れました
勝敗的には
甲乙つけがたい感じでしたが
個人的には負けた感が強いです
思えば初めて「飛龍」さんと対戦した約一週間後でした
おこがましいので言える立場でないですが
今日あの時間に鳴った防災放送のサイレンを聞いていて
少し厳かになったのも事実です
いろんな出会いを大切にしたいと
感じる一日でした
2012年03月05日
徒然に
動画記事はこのままかも
昨日はTTFでのゲームでした
出かけに小雨でしたが
勢いで行ってみればなんとかなるものです
しっかし寒かった・・・
今回の反省
ちょっと意図的に組み合わせをされてのゲームでした
しかも人数差をつけて
3対5かな最大で
実感として難しいゲームが多かったです
当方は3の方でしたが
2人差という状況がかなりのアドバンテージで
崩せなかったというのが本音ですし
現状では難しいですね
もう少し考えたいことや
打ち合わせも必要ですが・・・
個人で倒す技術
少数で倒す技術
チームで倒す技術
この意味と使いどころが
ちょっと混沌としているイメージでした
もっと自由に考えていいと思うんですが
少しだけ当方なりに整理して・・・
当方の考えですが
個人で倒す技術というのは
ベースとなる技術だと思います
トレーニング的にやっている反射的にサイトインしてダブルタップや
走り方・隠れ方・撃ち方・個人的な練習ができるものです
もちろんこれが高水準でできれば最高ですが
チーム戦である以上単独ではあまり意味をなさないと思います
(逆に言えば全体があるレベルだとすごいことになりそうです)
単純に多数対1では勝つことが難しいということです
もちろん勝てる人もいると思いますが
実は巧みに1対1の状況を作っているのだと思っています
そこに心理的なプレッシャーやクリエイティブな(サッカーで言う創造的なプレー?)
動きが重なっていきます
少数で倒す技術というのは
まさに2マンセルとか3マンセルといった1対多数を作り出す技術です
言い換えると連携と言われてると思います
ここにも少し種類があり
1に対しての動きと多数に対しての動きで差があると思います
単純に1に対して役割を付けるとすれば
「足止め兼目標」「落とし」となるでしょう(2マンセルですが・・・)
相手に対し撃たれているプレッシャーを与え自分に注意を惹かせて情報を与えない役と
情報を与えず絶対圏まで近づき落とす役となります
こう書くとわかりますが
実は小さな陽動になるわけです
これは意図がなかったとしても
味方に合わせて連携できることもあります
小さな約束事と自分が相手と同じ状況の場合何が嫌なのかを考えればいいわけです
多数に対して少数で倒すというのは基本的にはリスクの大きい事例ですが
どうしてもしなければならない場合もあるはずです
その場合最小の犠牲で最大の効果を上げるのであれば
最初の飛び出し役に続いて別方向からのフォロー(刹那の差をつける感じ)が必要です
相手は飛び出してくれば注目してしまいます
相手が見ている間は隙が生まれる(死角が増えてる)と感じチャンスと捉えることもできます
もちろん犠牲の上でというのはリスクもでかいですが
進行するために必要な場合もあると思うのです
これも一種陽動的な戦術ですね
チームで倒す技術というのは
そこからフィールド全体を使った陽動であったり
先ほどの2マン3マンセルを複数作りお互いの連携という意味です
おそらくこの場合
倒すというよりは有利なポジションに進ませることや
相手に対して注目させることで
何かを隠すという感じだと思います
さてまぁ昨日の反省ですが
当方は待つ場面で待てなかったりで
いいところがなかった感じです
なので大きいことは言えませんが
感心したことが一つ
相手の動きや位置の予想と実際の位置のズレが恐ろしく精度が高い
場合味方の位置や状態から
上記で言う少数で倒す形に持ち込めるのはさすがだと思いました
書き方として問題があるかもしれませんが
「後の先」とでも言いますか
あとからの動きなのに先が取れる感じです
あれは勝てませんし出し抜けません・・・・
わからない人にはさっぱりですね この記事は・・・・
昨日はTTFでのゲームでした
出かけに小雨でしたが
勢いで行ってみればなんとかなるものです
しっかし寒かった・・・
今回の反省
ちょっと意図的に組み合わせをされてのゲームでした
しかも人数差をつけて
3対5かな最大で
実感として難しいゲームが多かったです
当方は3の方でしたが
2人差という状況がかなりのアドバンテージで
崩せなかったというのが本音ですし
現状では難しいですね
もう少し考えたいことや
打ち合わせも必要ですが・・・
個人で倒す技術
少数で倒す技術
チームで倒す技術
この意味と使いどころが
ちょっと混沌としているイメージでした
もっと自由に考えていいと思うんですが
少しだけ当方なりに整理して・・・
当方の考えですが
個人で倒す技術というのは
ベースとなる技術だと思います
トレーニング的にやっている反射的にサイトインしてダブルタップや
走り方・隠れ方・撃ち方・個人的な練習ができるものです
もちろんこれが高水準でできれば最高ですが
チーム戦である以上単独ではあまり意味をなさないと思います
(逆に言えば全体があるレベルだとすごいことになりそうです)
単純に多数対1では勝つことが難しいということです
もちろん勝てる人もいると思いますが
実は巧みに1対1の状況を作っているのだと思っています
そこに心理的なプレッシャーやクリエイティブな(サッカーで言う創造的なプレー?)
動きが重なっていきます
少数で倒す技術というのは
まさに2マンセルとか3マンセルといった1対多数を作り出す技術です
言い換えると連携と言われてると思います
ここにも少し種類があり
1に対しての動きと多数に対しての動きで差があると思います
単純に1に対して役割を付けるとすれば
「足止め兼目標」「落とし」となるでしょう(2マンセルですが・・・)
相手に対し撃たれているプレッシャーを与え自分に注意を惹かせて情報を与えない役と
情報を与えず絶対圏まで近づき落とす役となります
こう書くとわかりますが
実は小さな陽動になるわけです
これは意図がなかったとしても
味方に合わせて連携できることもあります
小さな約束事と自分が相手と同じ状況の場合何が嫌なのかを考えればいいわけです
多数に対して少数で倒すというのは基本的にはリスクの大きい事例ですが
どうしてもしなければならない場合もあるはずです
その場合最小の犠牲で最大の効果を上げるのであれば
最初の飛び出し役に続いて別方向からのフォロー(刹那の差をつける感じ)が必要です
相手は飛び出してくれば注目してしまいます
相手が見ている間は隙が生まれる(死角が増えてる)と感じチャンスと捉えることもできます
もちろん犠牲の上でというのはリスクもでかいですが
進行するために必要な場合もあると思うのです
これも一種陽動的な戦術ですね
チームで倒す技術というのは
そこからフィールド全体を使った陽動であったり
先ほどの2マン3マンセルを複数作りお互いの連携という意味です
おそらくこの場合
倒すというよりは有利なポジションに進ませることや
相手に対して注目させることで
何かを隠すという感じだと思います
さてまぁ昨日の反省ですが
当方は待つ場面で待てなかったりで
いいところがなかった感じです
なので大きいことは言えませんが
感心したことが一つ
相手の動きや位置の予想と実際の位置のズレが恐ろしく精度が高い
場合味方の位置や状態から
上記で言う少数で倒す形に持ち込めるのはさすがだと思いました
書き方として問題があるかもしれませんが
「後の先」とでも言いますか
あとからの動きなのに先が取れる感じです
あれは勝てませんし出し抜けません・・・・
わからない人にはさっぱりですね この記事は・・・・