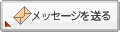2014年03月29日
徒然に
なんだかんだでもう七年くらいブログを書いてきてますので
現時点での当方の考えを少しまとめようかと・・・・
基本的に当方のスタンスは
「兵は鬼道なり」と「サバイバルゲームは情報戦」が主題です
「兵は鬼道なり」は孫子の言葉らしいです
意味としては「戦いはだましあいである」とのこと
「だます」と「だまされる」と二極化すれば
結局のところ主導権の話だと思うわけです
主導権(イニシアチブ)は重要です
サバイバルゲームにおいてはチーム単位の主導権とセル単位の主導権と
個人単位の主導権と三つあると思っています
チーム単位の主導権とは戦力が強いほうになると思います
この戦力というのは「経験」や「身体能力」ではなく
シンプルに「数」であると思っています
サバイバルゲームの特徴として時間経過とともに人数が減っていくルールがあるわけです
これはそのまま両チームの戦力バランスが崩れることを意味します
結果的に少ない戦力は劣勢になり多い戦力は優勢になります
セル単位の主導権とはチームよりは少ないが個人よりは多い単位
うまく言葉が見つからないのでセルと表記しますが
セル同士(例えば10人チームでのゲームにおいて局地的に3人対3人の状況)
が ぶつかったときにもどちらかに主導権はあるはずです
チームのように人数差で主導権を取る場合とポジションの配置でとる場合
連携や陽動で主導権を握る場合があると思います
個人単位の主導権は
相手に対し優勢に攻撃を仕掛けられることです
ここでポイントなのは
優勢に攻撃できることであり
個人技術も含まれますがそれだけではないということです
たとえ20mで100円玉を当てる技術があっても
優勢に攻撃できなければ宝の持ち腐れとなるわけです
個人でのイニシアチブの取り合いに勝つことができれば
セルでのイニシアチブにつながり
それはチームとしてのイニシアチブにつながるわけです
先ほど個人技術という言葉を出しましたが
個人技術というのは正確に撃つことだと思います
この辺はタクトレ等でいろいろ方法があると思いますので割愛しますが
当方は一瞬でも早く相手より準備することだと思います
例えば単純に的に当てるというのは狙って撃つことができれば
銃の性能を無視すればだれでもできます
さらに素早く構えて撃つというのも練習は必要ですが
できる技術だと思います(当方は苦手ですが・・・)
しかしゲームではなかなかできません(当たりません)
これは無理な体勢だったり慌てたりプレッシャーのかかる状況だったり
いろんな要素から普段の構えができないことが多いように感じます
(もちろん動く的を当てるわけですから難しいのですが・・・)
当方のいう個人単位のイニシアチブは普段の構えができない要素を少なくして
逆に相手に普段の構えができないようにすることが
イニシアチブをとることだと思います
文章で説明するのは難しいですが
相手がひるむ瞬間(自身が撃たれない状況)から構えて狙っておき 相手が出てきたところを撃つことだと思います
特に昨今は有料フィールドでのゲームが多いことを考えると
人工物のバリケードが多いわけです
そうすると相手は位置やタイミングを確認するために確実に頭が出るわけですから
先に構えて待っているほうがアドバンテージを持っているわけです
ここでバリケードというものの当方の考え方ですが
バリケードは安全です
撃たれても防ぐことができます
しかし隠れることはできないわけです
上でも書いてますが相手を確認しようとすれば必ず頭が出ます
ブッシュのように相手からばれにくいということはないので
位置情報を得やすいということを頭に入れる必要があります
閑話休題ですね
ここでサバイバルゲームは情報戦の話
このブログではサバイバルゲームの情報は二種類上げています
一つは位置情報(敵味方双方)もう一つは心理情報(造語です)だと思います
位置情報はそのまま相手がどこにいるかと味方がどこにいるかです
セルやチームのイニシアチブを考えた時に
どういう形にせよ分断し数をかけて各個撃破がセオリーです
実際とは違いますが
統計学上での公式に「ランチェスターの定理」と呼ばれているものがあります
詳しくは分かりませんが当方の解釈だと「自軍の損害をゼロにして相手を倒すには相手の戦力の三倍が必要」
ということだそうです
この公式が是とすれば一人倒すのに必要な戦力は三人となるわけです
少し難しい話ですが
TTFのマスターが導き出したプレート理論というものがあります
詳しくはTTFで確認するとよいと思いますが
同じ数同士のゲーム中自分と撃ち合う相手は一人です。これを1プレートとすれば
自軍の人数分プレートがあるということです
ここで肝心なのは複数相手にしている場合でも瞬間的には一人と撃ち合っているということです
先ほどの「ランチェスターの定理」に照らし合わせれば
1対1では五分の勝敗確率です(戦力を減らすための撃ち合いの場合)
もちろん主導権を取るほうが強いことを知っていれば
知っている人が有利ですがお互い知っている場合主導権の取り合いに終始します
そこでプレートとプレートの間に味方が入ることで瞬間的に2対1もしくは3対1の状況を作り出す
動きがプレート理論の根本だと思います
そのための技術として
相手と自分との間にある複数のバリケードを目隠しまたは弾を防ぐ目的として使い
いいポジション(複数のプレートに攻撃できる位置)に移動して
複数対1という状況を作るわけです
よくいいポジションという言葉を聞きますが
具体的に何がいいのかわからないことが多いです
同じように援護とかも具体的に何をするのかわからない言葉は
ゲームの中でよく出ます
この辺もきっちりと意味づけすることが連携への第一歩だと思います
これまた閑話休題
このプレート理論やランチェスターの定理をうまく使うにしても
相手の位置と味方の位置がわからないと使えません
また自分だけ知っているという状況でも同じです
相手の位置を正確に見極め自軍に伝えて相互共有することが
必要ということです
心理情報というのは
勝手に当方が言っているだけです
意味合いとして
見えない相手が何をしているかを想定するということです
特に個人単位の主導権を奪うために必要な情報となります
バリケードの裏は見えないと先ほど書きましたが
情報だけは分かることがあります
たとえばバリ裏の相手が撃っている音
銃口の向き(撃っている方向)
この情報は重要です
特に個人単位でイニシアチブを取り
さらに倒すにはリスクを低くする必要があります
そのため撃っている方向と逆から進行または射撃等の
小さいですがリスクを減らす手段を選択する指標になるわけです
この情報も味方と相互理解できてるとリスクがさらに減ります
ただチーム全体で共有というよりはセル単位ぐらいで共有し
連携しあうことが多いと思います
先ほど書いた連携について
連携の具体的な意味はわからないのですが
当方的には基本的に2つあると思っています
一つは縦の連携
もう一つは横の連携
縦の連携とは
自分または味方がポジションを変えたいときに
ポジションを変えるタイミングと時間を作り出す動きです
例えばですが相手に撃たれていて動けない場合
別の味方が撃っている相手を撃つことで射撃をやめさせ
バリケードに張り付かせること(イニシアチブをとること)で目隠しさせてタイミングと時間を作り出す
感じでしょうか
どちらかといえば移動することがメインとなります
横の連携は
相手を倒すために味方と逆方向からフォローに入る形
例えばですがバリ裏にいる相手を倒すために味方と逆方向から進行し攻撃する感じでしょうか
どちらかといえば陽動的な形で
相手に選択肢を複数与えて混乱させる形です
この二つが複雑に絡み合いながらゲームは進行していくわけですが
二つに共通していることは
連携とは相手に対し撃つことで無力化させそのタイミングや時間を使い次の準備をする動きのこと
これが連携の基本ベースとなるわけです
かなり基本的な部分ですが
当方がゲームをするうえでベースになっている部分です
最初に書いた「兵は鬼道なり」=イニシアチブを取るとすれば
そのために「情報を得る」ことが必要になります
ここからもっと複雑に考えます
スタイルの話です
「待ち」というスタイル
当方が勝手に読んでいますが
チームないし個人でのスタイルとして「待ち」というのがあります
相手がテリトリーに入ってくるまで待ち倒すスタイルです
特にブッシュ戦はこの「待ち」スタイルのバリエーションでゲームが進みます
例えばスタートダッシュ後会敵する直前に隠れ相手が来たところを撃つスタイルって見たことありませんか
これも「待ち」なわけです
上記で書いたように位置情報は重要です
相手に位置を知られずこちらが把握している状況は
かなり大きなアドバンテージを持っていることになります
実際に経験上ですが
この待ちスタイルとゲームすると時間切れが多くなります
攻める必要はあるのですが情報がわからず
進めなくなるわけです
ただこの待ちスタイルはフラッグを取るには不向きです
待ちスタイルには待ちスタイルで対抗すると
何の動きもない膠着戦になってしまい先に動いたほうが
アドバンテージを失うわけです
当方はゲームの中で最強の戦術だと思っていますが
勝てる勝率は低くなる気がします(うまく出し抜けて連携すると勝てますが)
このような相手にはある程度の数的優位を作り
位置を自ら暴露させる必要があります
相手に撃たせて位置を特定するわけです
撃たなければならない状態を作る訳です
これもリスク的にはかなり高いものになります
味方の損害を利用して相手の情報を得るわけですから
ただこうしないと情報を全く得られない状況もあるわけです
先の先と後の先
速攻と遅攻のことです
攻め方のセオリーとして
縦方向の形でこの二種類だと思います
これはゲームの進行状況や相手の配置により調整する必要があるので
その都度対応する形になります
時間の使い方
フラッグ戦のゲーム時間はおそらく15分が多いと思います
当方は時間の流れにおいてその工程があると思っています
最初はポジション
次が相手戦力を減らす
最後がフラッグアタック
これはうまくいって攻め込み勝つ状態の時間の流れです
これが劣勢になると
最後が時間稼ぎとなるわけです
単純に15分を三等分すれば
最初の5分でポジションにつき
次の5分で相手を減らし
最後の5分でフラッグアタックとなりますが
そうはうまくいかないわけです
しかし時間経過と工程を味方チームで共有していれば
時間経過とともに何をすべきかわかるので
連携への意思疎通がしやすくなるわけです
閑話休題です
速攻は相手との会敵ライン(造語)
よりも相手陣地に入り込む形です
会敵ラインとはスタート時から相手が倒せる距離での撃ち合いが始まる位置を
そう呼んでいます
これはフィールドによっても違いますが
だいたい同じ位置になってくるイメージが経験上あります
そのラインから相手陣地に早い段階で入っていければ速攻になり
後から入っていければ遅攻となるわけです
横方向の攻めかたのセオリーとして迂回というものがあります
本隊とは別に少人数で相手の弱い部分(フィールドのライン際)から
攻めこみ後に本体と合流する感じです
これは非常に高度で
相手の弱い部分がわかり
進行して倒し味方と連携するわけですから
相当な練習が必要です
ただ部分的には通常のゲームでも認識なくやっていることが多いです
初めてのフィールドで攻めるとき
どこに行きますか?
正解はないのですが当方的にはフィールドライン際を進みます
もちろん中央の時もありますが
最初のゲームはライン際にしてます
ライン際って索敵範囲が狭くなるわけです
絶対に相手の居ないエリアなので
正面と中央方向のみに集中することができます
特に見通しの悪いブッシュ系のフィールドでは
かなり有効だと経験上思います
フィールドの形状も把握しやすいですし
閑話休題です
撃つことの意味
もちろん相手を倒すのが目的ですが
上でも書いたように
撃つことで時間や目隠しを作ることができる
訳です
現在の風潮で弾数を撃つゲームは
あまりいい評価を受けませんが
ゲームのなかで唯一
自身が相手にプレッシャーを与えられる手段な訳です
この意味を正確に理解すると
進行するリスクを減らすことや
倒す場合のリスクも減りますし
連携の基本的な初歩動作に繋がるわけです
勝者と敗者に何の違いがあるのでしょうか
おそらくですが明確な違いはないと思います
勝負は水物といいますし
鉄砲も昨今はノーマルでも十分な性能があるわけです
おそらくですが鉄砲の性能の劇的変化は今後少ないと思います
ガスから電動のようなインパクトはないでしょう
フィールドも昔のように裏山や河川敷などはあり得ないでしょう
有料フィールドでのゲームが主だと思います
そして特色はあるにせよ 人工物のバリケードでのゲームが主になるでしょう
ある意味ですべてイコールのコンディションなわけです
しかし勝敗は付きます
当方的には昨今のCQBやらタクトレやらがその走りだと思うのですが
今後は個人技量またはチーム技量が優劣の基準になると思っています
(当てが外れてほしい気もしますが・・・・)
そうなったときに7年の記事が生かせるといいなぁと
取らぬ狸の皮算用的にほくそ笑むわけです
ただ机上の空論である
このブログを実践し評価される時が来るのが
楽しみであり怖くもあるわけです
現時点での当方の考えを少しまとめようかと・・・・
基本的に当方のスタンスは
「兵は鬼道なり」と「サバイバルゲームは情報戦」が主題です
「兵は鬼道なり」は孫子の言葉らしいです
意味としては「戦いはだましあいである」とのこと
「だます」と「だまされる」と二極化すれば
結局のところ主導権の話だと思うわけです
主導権(イニシアチブ)は重要です
サバイバルゲームにおいてはチーム単位の主導権とセル単位の主導権と
個人単位の主導権と三つあると思っています
チーム単位の主導権とは戦力が強いほうになると思います
この戦力というのは「経験」や「身体能力」ではなく
シンプルに「数」であると思っています
サバイバルゲームの特徴として時間経過とともに人数が減っていくルールがあるわけです
これはそのまま両チームの戦力バランスが崩れることを意味します
結果的に少ない戦力は劣勢になり多い戦力は優勢になります
セル単位の主導権とはチームよりは少ないが個人よりは多い単位
うまく言葉が見つからないのでセルと表記しますが
セル同士(例えば10人チームでのゲームにおいて局地的に3人対3人の状況)
が ぶつかったときにもどちらかに主導権はあるはずです
チームのように人数差で主導権を取る場合とポジションの配置でとる場合
連携や陽動で主導権を握る場合があると思います
個人単位の主導権は
相手に対し優勢に攻撃を仕掛けられることです
ここでポイントなのは
優勢に攻撃できることであり
個人技術も含まれますがそれだけではないということです
たとえ20mで100円玉を当てる技術があっても
優勢に攻撃できなければ宝の持ち腐れとなるわけです
個人でのイニシアチブの取り合いに勝つことができれば
セルでのイニシアチブにつながり
それはチームとしてのイニシアチブにつながるわけです
先ほど個人技術という言葉を出しましたが
個人技術というのは正確に撃つことだと思います
この辺はタクトレ等でいろいろ方法があると思いますので割愛しますが
当方は一瞬でも早く相手より準備することだと思います
例えば単純に的に当てるというのは狙って撃つことができれば
銃の性能を無視すればだれでもできます
さらに素早く構えて撃つというのも練習は必要ですが
できる技術だと思います(当方は苦手ですが・・・)
しかしゲームではなかなかできません(当たりません)
これは無理な体勢だったり慌てたりプレッシャーのかかる状況だったり
いろんな要素から普段の構えができないことが多いように感じます
(もちろん動く的を当てるわけですから難しいのですが・・・)
当方のいう個人単位のイニシアチブは普段の構えができない要素を少なくして
逆に相手に普段の構えができないようにすることが
イニシアチブをとることだと思います
文章で説明するのは難しいですが
相手がひるむ瞬間(自身が撃たれない状況)から構えて狙っておき 相手が出てきたところを撃つことだと思います
特に昨今は有料フィールドでのゲームが多いことを考えると
人工物のバリケードが多いわけです
そうすると相手は位置やタイミングを確認するために確実に頭が出るわけですから
先に構えて待っているほうがアドバンテージを持っているわけです
ここでバリケードというものの当方の考え方ですが
バリケードは安全です
撃たれても防ぐことができます
しかし隠れることはできないわけです
上でも書いてますが相手を確認しようとすれば必ず頭が出ます
ブッシュのように相手からばれにくいということはないので
位置情報を得やすいということを頭に入れる必要があります
閑話休題ですね
ここでサバイバルゲームは情報戦の話
このブログではサバイバルゲームの情報は二種類上げています
一つは位置情報(敵味方双方)もう一つは心理情報(造語です)だと思います
位置情報はそのまま相手がどこにいるかと味方がどこにいるかです
セルやチームのイニシアチブを考えた時に
どういう形にせよ分断し数をかけて各個撃破がセオリーです
実際とは違いますが
統計学上での公式に「ランチェスターの定理」と呼ばれているものがあります
詳しくは分かりませんが当方の解釈だと「自軍の損害をゼロにして相手を倒すには相手の戦力の三倍が必要」
ということだそうです
この公式が是とすれば一人倒すのに必要な戦力は三人となるわけです
少し難しい話ですが
TTFのマスターが導き出したプレート理論というものがあります
詳しくはTTFで確認するとよいと思いますが
同じ数同士のゲーム中自分と撃ち合う相手は一人です。これを1プレートとすれば
自軍の人数分プレートがあるということです
ここで肝心なのは複数相手にしている場合でも瞬間的には一人と撃ち合っているということです
先ほどの「ランチェスターの定理」に照らし合わせれば
1対1では五分の勝敗確率です(戦力を減らすための撃ち合いの場合)
もちろん主導権を取るほうが強いことを知っていれば
知っている人が有利ですがお互い知っている場合主導権の取り合いに終始します
そこでプレートとプレートの間に味方が入ることで瞬間的に2対1もしくは3対1の状況を作り出す
動きがプレート理論の根本だと思います
そのための技術として
相手と自分との間にある複数のバリケードを目隠しまたは弾を防ぐ目的として使い
いいポジション(複数のプレートに攻撃できる位置)に移動して
複数対1という状況を作るわけです
よくいいポジションという言葉を聞きますが
具体的に何がいいのかわからないことが多いです
同じように援護とかも具体的に何をするのかわからない言葉は
ゲームの中でよく出ます
この辺もきっちりと意味づけすることが連携への第一歩だと思います
これまた閑話休題
このプレート理論やランチェスターの定理をうまく使うにしても
相手の位置と味方の位置がわからないと使えません
また自分だけ知っているという状況でも同じです
相手の位置を正確に見極め自軍に伝えて相互共有することが
必要ということです
心理情報というのは
勝手に当方が言っているだけです
意味合いとして
見えない相手が何をしているかを想定するということです
特に個人単位の主導権を奪うために必要な情報となります
バリケードの裏は見えないと先ほど書きましたが
情報だけは分かることがあります
たとえばバリ裏の相手が撃っている音
銃口の向き(撃っている方向)
この情報は重要です
特に個人単位でイニシアチブを取り
さらに倒すにはリスクを低くする必要があります
そのため撃っている方向と逆から進行または射撃等の
小さいですがリスクを減らす手段を選択する指標になるわけです
この情報も味方と相互理解できてるとリスクがさらに減ります
ただチーム全体で共有というよりはセル単位ぐらいで共有し
連携しあうことが多いと思います
先ほど書いた連携について
連携の具体的な意味はわからないのですが
当方的には基本的に2つあると思っています
一つは縦の連携
もう一つは横の連携
縦の連携とは
自分または味方がポジションを変えたいときに
ポジションを変えるタイミングと時間を作り出す動きです
例えばですが相手に撃たれていて動けない場合
別の味方が撃っている相手を撃つことで射撃をやめさせ
バリケードに張り付かせること(イニシアチブをとること)で目隠しさせてタイミングと時間を作り出す
感じでしょうか
どちらかといえば移動することがメインとなります
横の連携は
相手を倒すために味方と逆方向からフォローに入る形
例えばですがバリ裏にいる相手を倒すために味方と逆方向から進行し攻撃する感じでしょうか
どちらかといえば陽動的な形で
相手に選択肢を複数与えて混乱させる形です
この二つが複雑に絡み合いながらゲームは進行していくわけですが
二つに共通していることは
連携とは相手に対し撃つことで無力化させそのタイミングや時間を使い次の準備をする動きのこと
これが連携の基本ベースとなるわけです
かなり基本的な部分ですが
当方がゲームをするうえでベースになっている部分です
最初に書いた「兵は鬼道なり」=イニシアチブを取るとすれば
そのために「情報を得る」ことが必要になります
ここからもっと複雑に考えます
スタイルの話です
「待ち」というスタイル
当方が勝手に読んでいますが
チームないし個人でのスタイルとして「待ち」というのがあります
相手がテリトリーに入ってくるまで待ち倒すスタイルです
特にブッシュ戦はこの「待ち」スタイルのバリエーションでゲームが進みます
例えばスタートダッシュ後会敵する直前に隠れ相手が来たところを撃つスタイルって見たことありませんか
これも「待ち」なわけです
上記で書いたように位置情報は重要です
相手に位置を知られずこちらが把握している状況は
かなり大きなアドバンテージを持っていることになります
実際に経験上ですが
この待ちスタイルとゲームすると時間切れが多くなります
攻める必要はあるのですが情報がわからず
進めなくなるわけです
ただこの待ちスタイルはフラッグを取るには不向きです
待ちスタイルには待ちスタイルで対抗すると
何の動きもない膠着戦になってしまい先に動いたほうが
アドバンテージを失うわけです
当方はゲームの中で最強の戦術だと思っていますが
勝てる勝率は低くなる気がします(うまく出し抜けて連携すると勝てますが)
このような相手にはある程度の数的優位を作り
位置を自ら暴露させる必要があります
相手に撃たせて位置を特定するわけです
撃たなければならない状態を作る訳です
これもリスク的にはかなり高いものになります
味方の損害を利用して相手の情報を得るわけですから
ただこうしないと情報を全く得られない状況もあるわけです
先の先と後の先
速攻と遅攻のことです
攻め方のセオリーとして
縦方向の形でこの二種類だと思います
これはゲームの進行状況や相手の配置により調整する必要があるので
その都度対応する形になります
時間の使い方
フラッグ戦のゲーム時間はおそらく15分が多いと思います
当方は時間の流れにおいてその工程があると思っています
最初はポジション
次が相手戦力を減らす
最後がフラッグアタック
これはうまくいって攻め込み勝つ状態の時間の流れです
これが劣勢になると
最後が時間稼ぎとなるわけです
単純に15分を三等分すれば
最初の5分でポジションにつき
次の5分で相手を減らし
最後の5分でフラッグアタックとなりますが
そうはうまくいかないわけです
しかし時間経過と工程を味方チームで共有していれば
時間経過とともに何をすべきかわかるので
連携への意思疎通がしやすくなるわけです
閑話休題です
速攻は相手との会敵ライン(造語)
よりも相手陣地に入り込む形です
会敵ラインとはスタート時から相手が倒せる距離での撃ち合いが始まる位置を
そう呼んでいます
これはフィールドによっても違いますが
だいたい同じ位置になってくるイメージが経験上あります
そのラインから相手陣地に早い段階で入っていければ速攻になり
後から入っていければ遅攻となるわけです
横方向の攻めかたのセオリーとして迂回というものがあります
本隊とは別に少人数で相手の弱い部分(フィールドのライン際)から
攻めこみ後に本体と合流する感じです
これは非常に高度で
相手の弱い部分がわかり
進行して倒し味方と連携するわけですから
相当な練習が必要です
ただ部分的には通常のゲームでも認識なくやっていることが多いです
初めてのフィールドで攻めるとき
どこに行きますか?
正解はないのですが当方的にはフィールドライン際を進みます
もちろん中央の時もありますが
最初のゲームはライン際にしてます
ライン際って索敵範囲が狭くなるわけです
絶対に相手の居ないエリアなので
正面と中央方向のみに集中することができます
特に見通しの悪いブッシュ系のフィールドでは
かなり有効だと経験上思います
フィールドの形状も把握しやすいですし
閑話休題です
撃つことの意味
もちろん相手を倒すのが目的ですが
上でも書いたように
撃つことで時間や目隠しを作ることができる
訳です
現在の風潮で弾数を撃つゲームは
あまりいい評価を受けませんが
ゲームのなかで唯一
自身が相手にプレッシャーを与えられる手段な訳です
この意味を正確に理解すると
進行するリスクを減らすことや
倒す場合のリスクも減りますし
連携の基本的な初歩動作に繋がるわけです
勝者と敗者に何の違いがあるのでしょうか
おそらくですが明確な違いはないと思います
勝負は水物といいますし
鉄砲も昨今はノーマルでも十分な性能があるわけです
おそらくですが鉄砲の性能の劇的変化は今後少ないと思います
ガスから電動のようなインパクトはないでしょう
フィールドも昔のように裏山や河川敷などはあり得ないでしょう
有料フィールドでのゲームが主だと思います
そして特色はあるにせよ 人工物のバリケードでのゲームが主になるでしょう
ある意味ですべてイコールのコンディションなわけです
しかし勝敗は付きます
当方的には昨今のCQBやらタクトレやらがその走りだと思うのですが
今後は個人技量またはチーム技量が優劣の基準になると思っています
(当てが外れてほしい気もしますが・・・・)
そうなったときに7年の記事が生かせるといいなぁと
取らぬ狸の皮算用的にほくそ笑むわけです
ただ机上の空論である
このブログを実践し評価される時が来るのが
楽しみであり怖くもあるわけです